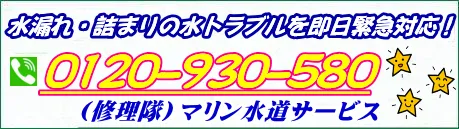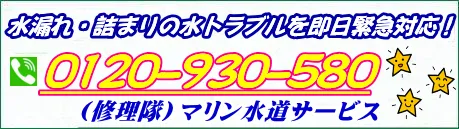専門用語収録目次:鉛製給水管

専門用語一覧
鉛製給水管
鉛製給水管とは、その名の通り鉛(Pb)を素材として作られた給水用の配管であり日本では明治時代から昭和40年代にかけて広く使用されていた歴史を持つ。加工性に優れており柔らかいため曲げやすく工具による施工も容易だったことから水道配管の主流材料のひとつとして採用されていた。しかし、鉛には人体への健康リスクがあることが次第に明らかになり現在では使用が禁止または厳しく制限されている。
●鉛製給水管の特徴
鉛は非常に柔らかく融点も比較的低いため、鋳造や加工がしやすいという利点がある。古くは地中配管において複雑な形状の配管が求められる現場や狭小な空間に設置する際などに多用された。さらに、鉛は耐腐食性も一定程度持ち合わせており、当時の技術水準では耐久性も評価されていた。しかし、その柔らかさが裏目に出ることもあった。たとえば、地震や地盤沈下による衝撃で変形しやすく水漏れやひび割れの原因となることもあった。加えて、内部に水が滞留すると鉛が水中に溶出するという重大な問題もある。
●健康への影響
鉛の最大の問題は人体への健康リスクである。鉛は微量であっても体内に蓄積され長期的な健康被害を引き起こす可能性がある。特に乳幼児や胎児に対する影響が深刻で神経発達障害、知能の低下、学習障害などを引き起こすことが国内外の研究で報告されている。成人でも慢性的な鉛中毒により高血圧、腎機能障害、消化器系の異常などが起こるリスクがある。鉛が水に溶出する量は、水のpH、温度、滞留時間、流速などによって左右される。古い建物では夜間や長期不在時に配管内の水が停滞し朝一番の水道水から鉛が検出されるケースがあり、1990年代以降、厚生労働省や水道事業者は「朝一番の水はしばらく流してから使用する」ことを推奨してきた。
●法的規制と禁止措置
日本では、1970年代後半から鉛製給水管の使用による健康被害が社会問題化し、それに伴って水道法や建築基準法の改正が行われた。具体的には、1980年代から新規建設における鉛管の使用が原則として禁止され、さらに1992年には給水装置の技術的基準として鉛製管の使用を避けるよう明記された。現在では、鉛製給水管は「既存不適格建築物」として扱われ新設・更新工事ではステンレス鋼管、塩化ビニルライニング鋼管、ポリエチレン管などの安全な材質への置換が義務付けられている。また、鉛の水質基準も厳格に定められており水道水1リットルあたり0.01mg以下とされている。
●交換工事と実態
多くの自治体では、鉛製給水管の全廃を目指して計画的な交換工事を進めている。例えば東京都水道局や大阪市水道局では、住宅所有者の費用負担を軽減するための助成制度を設け、鉛管からステンレス管や樹脂管への交換を促進している。ただし、問題はすべての配管が行政の管理下にあるわけではないという点である。戸建住宅や集合住宅内の給水管、メーター以降の屋内配管は原則として所有者の管理責任であり、こうした「私有部分」に鉛管が残存しているケースが現在でも見受けられる。特に戦後すぐの時代に建設された住宅では、鉛管が使用されていた割合が高いため、注意が必要である。また、配管の外観から材質を判断するのは専門知識を要する。鉛管は他の金属管に比べて柔らかく、爪でこすれば銀白色の光沢が現れるといった特徴があるが、一般家庭での判別は難しく、水道業者による調査が推奨される。
●現在の対応と市民への注意喚起
厚生労働省や水道事業者は、鉛製給水管の残存について定期的に調査を行い残存箇所が確認された場合は速やかに更新を促すとともに必要に応じて水質検査や配管改修工事を実施している。また、自治体や水道局の公式ウェブサイトでは、鉛管の見分け方や交換手続き補助制度などが案内されており住民への情報提供も強化されている。
利用者に対しては、以下のような基本的な注意が呼びかけられている。
・朝一番や長期不在後は、数十秒程度水を流してから使用する。
・飲用水や調理水は浄水器を通すか給湯器からではなく水道の水を使用する。
・配管材が不明な場合は、水道業者に依頼して調査を受ける。
・改修工事やリフォームの際には、鉛製管の撤去・交換を依頼する。
●今後の展望と課題
鉛製給水管の完全撤去は、日本の水道インフラの老朽化問題とも深く関わっている。多くの地域で1950?70年代に整備された配管が耐用年数を超えつつあり鉛管だけでなく老朽化した鋼管などの全面的な更新が求められている。鉛製給水管に関する正確な情報が住民全体に行き渡っているとは限らないため啓発活動や定期的な点検体制の強化も重要である。とりわけ高齢者世帯や築年数の古い住宅が集中する地域では、自治体と連携した計画的な訪問調査が望まれる。
また、災害時には古い鉛管が破損するリスクも高く災害に強いインフラとしての更新も含めて今後の水道インフラ整備計画の中で優先順位をつけた対応が求められる。